お店に入ると、梢は風間社長からもらった真珠のネックレスを大切にロッカーの奥にしまい、メイクを直した。
「うちさー、道路に唾をはく男って好きじゃないんだよね。街で唾をはいてる人を見るとすごく嫌な気分になるよ。マジ、あれはないよね?」
同期の北川希子が言った。彼女はいつも明るく振るまい弱みを見せないタイプだが、震災で両親を亡くしていた。
「わかるわかる。うちも嫌だね」
「あとさー、うち、タトゥーあり派じゃないからタトゥー入れてる人もダメだね」
梢は隣で着がえている希子とのおしゃべりに夢中になり、ふたりは楽しくて子どものようにころころと笑った。いつものなんてことのない会話だった。
「なんで自分のこと”うち“って言うの? ”私“でしょ?」
希子の隣で着がえていた二年先輩のお姉さんが話に割りこんできた。お姉さんの指摘がふたりの笑いのつぼに入ってしまった。笑いをこらえようとする梢のえくぼが何度も出たり消えたりした。
「うちはさー」と学生時代に無意識に使っていた言葉を梢は初めて指摘された。
(そういえば、方言のイントネーションを演技レッスンで指摘されたことがあったっけ。学生氣分はとっくに抜けているはずなのに、希子と話すと学生時代にタイムスリップしてしちゃうなー。まだまだ、私って幼いのね)
二十三歳 七月
土曜日の夕方。
今日は、演技レッスンでひとりずつ発表する日だ。梢は、暗記した『外郎売の台詞』のコピーをかばんから出した。
『外郎売』とは、飲むと舌が回りだしてとまらなくなる丸薬『ういらう』を売るために、外郎売がそれを飲んでみせ早口言葉をどんどん言っていくという、二代目市川團十郎によって初演された歌舞伎十八番のひとつである。
日本では、俳優の養成所やアナウンサーの発声練習などに使われているらしい。
梢の番がきた。
前に出てみんなのほうを向く梢。いっせいに梢に注目が集まる。横で見ている講師。
(あれだけ練習したんだから、大丈夫……)
「よーい、スタート!」
「拙者親方と申すは、お立会の中に、御存じのお方もござりましょうが……」
感情も入れ、早口言葉が口からスラスラと出てきた梢は、自分なりにその世界を表現しきれた思いで満足感に浸った。
「カット! 吉川、自分でどうだった?」
「うまくできたほうだと思います」
「結構練習しただろ?」
「はい」
ようやくお昼から六時間続いた演技レッスンが終わった。梢はお店のほうは順調だったが、女優としてデビューが決まらない焦りを胸に、スタジオを出ようと重量感のある扉を押した。天井や壁や床がすべての音を吸い取ってしまうスタジオの扉の向こうは、あたり一面が白っぽく見えるほどの土砂降りだった。
(とっくに憂鬱な梅雨は終わったのに……)
梢は、腕に抱えたレッスンの台本がぬれないようかばんの奥にしまった。傘を持っていなかったので、ビニール傘を買うためコンビニを探したが見あたらず、小走りで近くのドトールまで走った。
(小降りになるまでしばらくここでまったりコーヒーでも飲んでいこう)
べちゃべちゃにぬれてしまった梢の髪は、泳いだあとのようだった。
梢はかばんからフェイスタオルを取りだし、水滴が染みこまないように軽くたたいて払い落とし、髪やTシャツの水滴を拭いた。早くしないと下着までぬれてしまいそうだった。
梢が先週のダンスレッスンで汗を拭くために入れていたフェイスタオル。使っていないのでよく吸いとるに違いないと思った。
雨にぬれて岩のりみたいにペチャンコになった髪から、シャンプーの甘ったるいストロベリーの香りが漂い梢の鼻をうった。
梢はドトールではいつもアイス宇治抹茶ラテと決めている。今日も例に漏れず、アイス宇治抹茶ラテを注文し、飲みおえるとグラスのすべての氷を口の中でガリガリかみくだいた。歯を突きさすような冷たい心地と音が好きで、真冬でも冷たい氷を食べるほどだ。貧血の女性は体が鉄分を欲してそういう状態になるらしく、人によっては赤い土を食べたくなることもあるらしい。アイス宇治抹茶ラテを飲みおえると雨にぬれた体がぶるりと震えた。
今度は体を温めるため、梢はホットコーヒーを注文した。
いちおう体に氣を使っている梢は、クリープを三分の一だけ入れトレイの隅に置いた。そのコーヒーをゆっくりかき混ぜ黒い液体が完全に薄茶色に変わったことを確認すると、梢はひと口すすった。コーヒーが得意でない梢でも、自然に体に染みいるような自然な味わいを楽しめた。
傘を持っていない人たちが次々と店内に入って来るのを、梢はぼんやりと見ていた。
一時間くらいたっただろうか、雨が少し優しくなったので今のうちに帰ることにした梢はドトールを出た。
駅に向かい歩いていると、見知らぬ男性が梢をめがけて走ってきた。尋常ではない表情だったので、梢は怖くなり早足で通りすぎようとした。
「モデルに興味ありませんか?」
黒いスーツにネクタイ姿のおなかが出ている男は、梢の目の前まで来ると名刺を梢に差しだした。
「すみません、興味ないです」
差しだされた名刺を見ながら淡々と答えると、その男がしつこく食いさがってきた。
「名刺だけでも受けとってもらわないと帰りません」
梢は言葉につまってしまった。よく見るとその男は、五十メートル走を全力で走りぬけたようにハアハアと呼吸が乱れていた。
「ありがとうございます」
小太りの怪しい男があまりにも食いさがってくるので、梢は名刺を受けとり、名前も確認せずCHANELの長財布にしまった。
梢は知らないうちに自分の世界をごちゃごちゃにしようと、パーソナルスペースに勝手に侵入してくる人間が苦手だった。二十三歳になった今でも同じタイプと接すると子ども時代の母とのトラウマがよみがえり、梢はパニックになりかける。心臓がバクバクと波うち、自分の体ではないように感じるのだ。
梢は胸をさすりながら慌てて駅のトイレに駆けこみ、いつも携帯しているラベンダーの精油を数滴手のひらに垂らした。それを両手の体温で温めるように包みこみ自分の胸に塗りたくってから鼻に手のひらを近づけて、その香りをたっぷりと肺に送りこんだ。
梢は何度も大きく深呼吸をした。
タスマニア産のラベンダーの精油。フランス産に比べ香りの最初にあるツンとした刺激がなく、少しワイルドで懐かしい野草の氣配をもっているので、梢は好んで使っていた。
多用途なラベンダーはリラックス効果が高く沈静沈痛作用や殺菌作用があり、今までの不安や恐怖がそれぞれの持ち場に戻って見えなくなってしまったかのように梢の心を落ちつかせたのだった。
誕生日を迎えて二十三歳になったばかりの自分のような小娘に、大の大人がなぜあんなに一生懸命になれるのか梢には不思議でもあった。
□■□∞∞────────────────────────────────∞∞□■□
続く……。
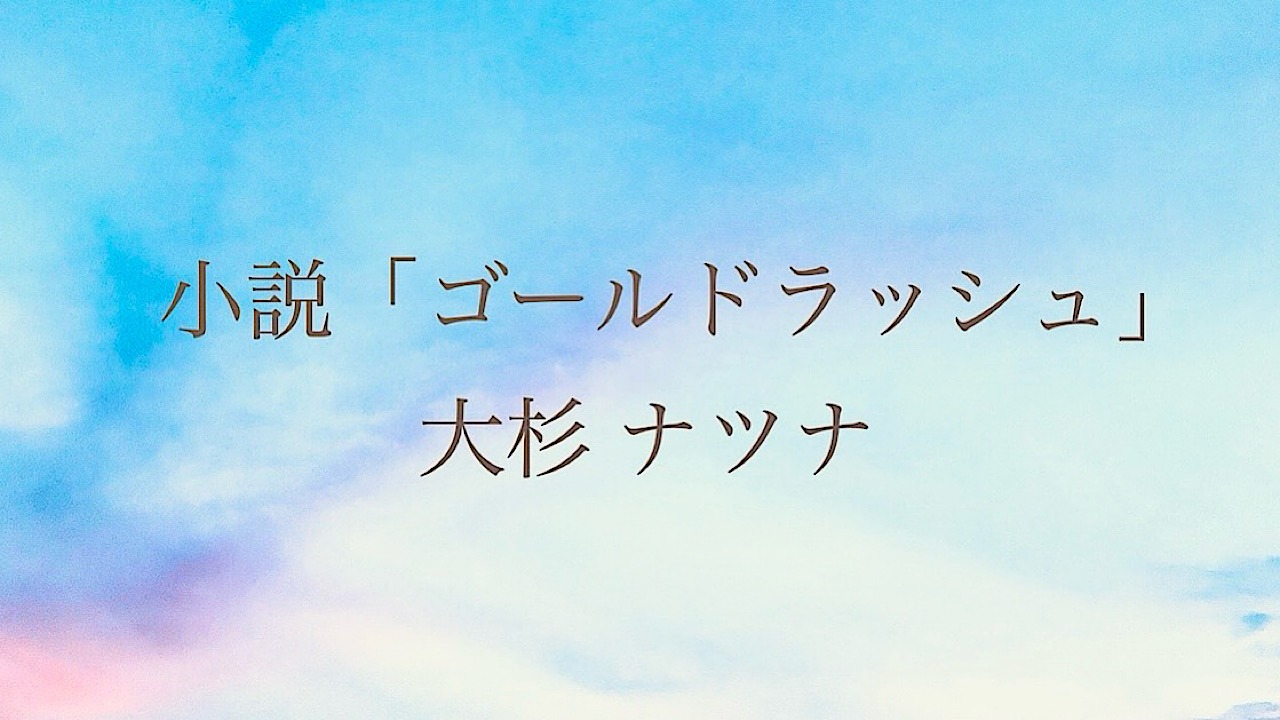
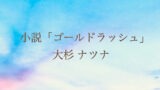
「自分を深く知る」ことをさまざまな角度から探求し、自分を癒やしていく過程で、生きづらさの原因がHSPという特性であることにたどりつきました。
このブログはHSPという特性に向き合いながら、結婚と天職を手に入れるまでの心の深海潜水夫記録です。
大人になってHSPを知り、ふに落ちた過去の思いを忘れずに書きとめておきたいと思い始めました。小説も書いています。
現在、工場で働くHSPアラフォーです。
あくまで、個人的考察です。