「今では会社の社長をやってるけど、若いころグレててホストやってた時期があるんだ。そこでもいろんな人間関係があったし、嫌がらせも山ほどあったよ。あんがい男のほうがネチネチしてるんだよ」
ワインを口に含み流しこむ風間社長の喉仏には、迫力があった。
(そんなふうには見えないけど……風間社長みたいな人でもいろんなものを背負っているなんて、人間はわからないものだなぁ)
梢は入店するとき、「ホステスは女優です。自分を磨き演じてください」と言われたことを思いだしていた。しかし、今は美酒の誘惑に身を任せて存分に酔ってしまいたい梢がいた。とうとうナンバーワンホステスを演じる女優ではなく素の自分が出てきてしまい、頭のなかでこれまでの人生が短編映画のように流れていき、高校を退学し上京したこと、映画で活躍する女優を目指してレッスンに通っていること、このお店が二店目だということ、そして今回のロッカーの件を梢は正直に話してしまった。
「まあ、あなたのことをねたむ人は何人もいるだろうね。ひとりしかナンバーワンにはなれないんだし。アイドルと一緒でファンが多くなればなるほど、アンチもいっぱい出てくるもんだよ。だから、その人の貴重な時間を使って粗探ししてくるんだから、ありがたく思ってほっておけばいい。そいつらを暇人だなあって思えばいいよ」
固い肩の凝りがスーッと溶けるような風間社長の優しい言い方のおかげか、血液と一緒に体中に赤いワインが流れ、梢は体の芯から幸せになる感じがした。
「はい、私はもっと上を目指したいんです。今とはまったく違う場所に行きたいんです」
格別においしい赤ワインの魔法にかかった梢は、多弁な自分をとめられなくなっていた。
風間社長は品があり梢が好きなA型だった。
年齢は五十代半ばくらいで、ロマンスグレーの髪が優しそうな雰囲氣を醸しだしていた。
(今度この風間社長に同伴に誘われたら、一緒にご飯を食べてみよう。そのときはおすしがいいな)
梢は勝手に決めていた。
「梢さん、明日風間社長にお礼の電話を差しあげてくださいね」
閉店後、いつもより梢が酔っているのを見かねた支配人は、必ずお礼の電話をするよう念をおした。
帰宅した梢は酔いが全身にまわったのか、メイクも落とさずそのまましわくちゃのベッドに倒れこむ。ひんやりと冷たいシーツがワインと風間社長との会話で火照った梢の体を氣持ちよく包みこんだ。
翌日、十二時をちょっと過ぎたころ、スマホの目覚ましが鳴った。まだワインが完全に抜けきっておらず、梢の頭に鈍い痛みが走った。
窓を開けると、冷たい風が梢の口からはきだされた白い息を散らした。世間はクリスマスに向かって日を追うごとに雰囲氣がにぎやかになってきている。
昼休みを狙って、梢は名刺とは別に渡された風間社長の携帯のほうにお礼の電話をかけた。
「お疲れさまです。吉川梢ですが、きのうはご指名ありがとうございました。いろんなお話が聞けて楽しかったです、ワインもごちそうさまでした」
「あっ、梢ちゃん? ちょうど昼休みで誰もそばにいなくてよかったよ。それにしても他人行儀だなぁ、きのうの感じで大丈夫だよ」
なぜか、梢はこの風間社長に対しては自分から同伴をお願いすることができなかった。だから次に会うのは、風間社長から同伴に誘われたときか来店したときだった。
電話を切ったあと、梢は少しばかり寂しくなってしまった。
(ほれてしまったの? ……仕事一筋の私が? まさかね……)
裸になった女がひとり鏡に写っていた。梢の乳房の盛り上がった半球の上には剥きだしになった青い静脈が透けて見え、スラリと伸びた脚の間に黒々とした細い毛が密生しているのが見えた。
無性にほしくなり、初めて梢はひとりエッチをした。クリスマスを迎えようとしている街の華やかさの影響ではなく本能がそうさせたのだった。
梢は、お店のお客との恋愛を考えたことはなかった。相手が独身でも既婚者でもだ。まして自分が愛人や浮気相手という立場になるのは、梢のプライドが許さなかった。
金持ちの愛人になり、ホステスを辞めて悠々自適な生活をおくっている元ホステスもいる。彼女には若いボーイフレンドが別にいるらしいが、それでもいいと相手に言われ愛人契約というものをしたらしい。
努力は嫌だ。頑張りたくない。面倒臭いのは嫌だ。これが彼女の口癖だった。
人生いろいろ、この世は男と女の化かしあいだ。
梢は、今まで築きあげてきた自分が崩れてしまうことを誰よりも知っていた。
きっと自分の魂の片割れに出会ったら、自分は冷静ではいられなくなるだろう。もしこの世に存在するのなら、梢は究極の魂の伴侶……ツインレイという存在に出会いたいと願っていた。それまでは中途半端な男性とくっつくよりも、氣持ちよくなるならひとりエッチのほうが手っ取り早いと梢は思っていた。
梢の頭から爪の先まで愛してくれる男性にしがみつき、自分のなかをぐちゃぐちゃにかきまぜてくれる男性が現れるまで、そして女優の夢をかなえるまで、梢は悶々としたときはベッドの中でひとりエッチですませるはずだった。
快感が押しよせてきてイキそうになるが、どうしていいかわからず梢は指をとめてしまう。
お互いセックスの相性がよければテクニシャンって言うのかもしれない。
梢がシャワーを浴びるため脱いだ下着には、白みがかった半透明のねっとりとしたものが残されていた。
そして、梢は何ごともなかったかのようにその火照った体にシャワーを浴びせ、身支度を始めた。
二十二歳 六月
ジメジメした梅雨の時期がやってきた。
来月の誕生日で二十三歳になる梢は、月島に引っ越していた。まだすべての荷解きが終わっておらず、部屋の中は洋服やCD、本や光熱費の請求書やらが散乱していた。
梅雨なので、途中で髪形が崩れないようにいつもより固めに美容院でセットした。白い着物を着た二十二歳の梢の肉体は性への憧れを隠しつつもぞくっとする色っぽさがあった。
今日は風間社長と同伴の日だ。カウンターのおすしをごちそうになり、とてもいい氣分で食事を終えた梢は、突然風間社長から誕生日プレゼントを渡された。
「はい、これ。ちょっと早いけど誕生日おめでとう」
「えっ、いいんですか?」
「きっと似合うと思うよ。開けてみてよ」
「はい、ありがとうございます」
梢は、長方形の箱に結ばれている赤いリボンをていねいにほどいてみた。
「わぁー、すてき! 私、真珠好きなんです」
「よかったら、今度会うときつけてきてくれないか?」
「はい、喜んで。ありがとうございます」
梢はまた風間社長に会えると思うと、頰が自然に緩んだ。今日は着物だけど、今度会うときはこのネックレスが似合う洋服にしようと思った。
続く……。
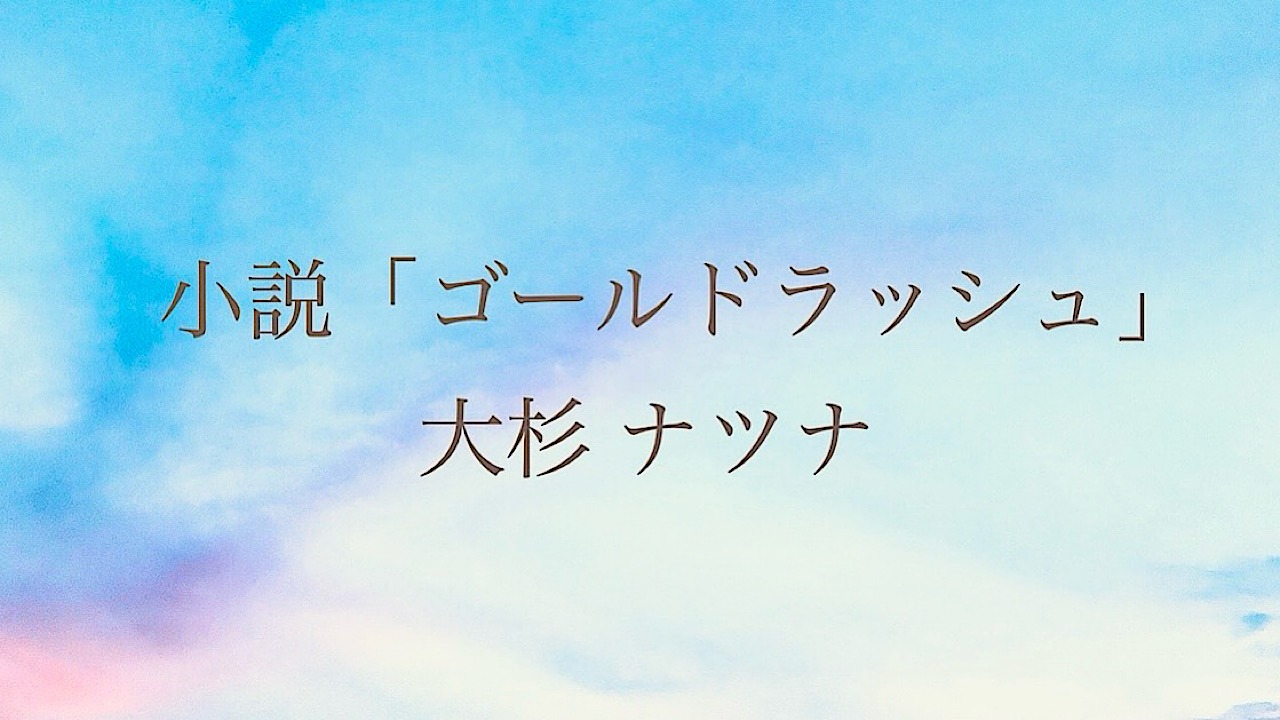
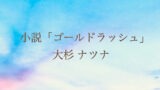
「自分を深く知る」ことをさまざまな角度から探求し、自分を癒やしていく過程で、生きづらさの原因がHSPという特性であることにたどりつきました。
このブログはHSPという特性に向き合いながら、結婚と天職を手に入れるまでの心の深海潜水夫記録です。
大人になってHSPを知り、ふに落ちた過去の思いを忘れずに書きとめておきたいと思い始めました。小説も書いています。
現在、工場で働くHSPアラフォーです。
あくまで、個人的考察です。