「ただいまー」
十三時ごろ。梢が玄関のドアを開けると家の奥からテレビの音が聴こえてきた。
(お母さん、耳が遠くなっているんだ……)
梢の声は母には聞こえていなかった。
梢はかばんをリビングのソファーに置き冷蔵庫から麦茶を出すと、グラスに氷を入れて一氣に飲みほした。
「ただいま。お母さんもお茶飲む?」
「おかえり。今はいいわ」
母は梢のほうをチラッと見ると、またテレビのほうに視線を戻した。
さっき冷蔵庫を開けてみたら、お中元でもらったであろう飲まない缶ビールがたくさん並んでいた。
(離婚して父はもういないというのに、誰が送ってくるのだろうか?)
年金生活しているわりには相変わらずたくさんの食材でいっぱいで、何も変わっていなかった。
聞いてみると母も昼食は食べおわっていたので、梢は一緒にテレビを観ることにした。
「去年もこんなに暑かったっけ?」
梢は会話がないのもなんだかなぁと思い、世間話をした。
「暑かったんじゃない? こっちはずっと雨が降らなくて久しぶりに降ったのよ」
「へーそうなんだ。お母さん、前に私が出たドラマ観た?」
「観たわよ」
「どうだった?」
「あんたが頑張ってる姿を見て、安心したわよ」
「それだけ?」
「そうよ」
(昔からの母を思えば、まあこんなもんだろう。
だから離婚するんだ。話題をそらそう……)
少しイラついた母にマズいと感じた梢は、昔から繰りかえされるパターンに内心うんざりしながらも、優しい母の言葉をどこかで期待していた。
「お母さん、昔テレビ局からインタビュー受けたこと覚えてる?」
女優の母としてテレビに映りうれしかった部分もあったんじゃないかと、梢はわざと聞いてみた。
「覚えてるわよ。びっくりしたわ」
「あーゆうときは、もっと氣が利いたことを言ってほしかったよ。全国で流れたんだよ、私が恥ずかしいじゃない?」
「あんたがしっかりしてないんだから、しょうがないじゃない。夕飯までちょっと昼寝でもしようかしら? 夕飯ができたら起こしてよ」
焼け石に水だった。
居間の窓ガラスについた水滴は、そのまま水の糸を引いて絶え間なく下に流れている。
隣の部屋に布団を敷くと、梢は母を布団まで連れていった。
母は介護が必要になってから、めっきり口数が少なくなったんじゃないかと梢は感じていた。
冷たく素っ気ないのは昔からだったが、年をとり介護が必要な母をそばで見ていると、梢の心は複雑だった。
ざまーみろ!という悪魔のような一面が梢のなかから顔を出す。また別の日には、子どもひとり育てるのは大変よね。私もひとりで大きくなったわけじゃないし、自由に動けなくなって落ちこんでいるのは母本人なんだからと、天使のような一面が顔を出す……。
梢は室内に干してある半乾きの母の洗濯物をそのままにして、風呂を掃除してから夕飯の支度をした。今日の夕飯はカレーだ。そこにちょっとしたサラダをつけてふたりで食べた。
母は食事中もずっと野球を観ていて、明らかに以前よりテレビのボリュームが大きくなっていた。
夕飯の片付けをしている間も、母はまるで梢がそこにいないみたいにずっと野球を観ていた。
「どっちが勝ってるの?」
「今、同点だよ」
「そうなんだ」
梢は、野球に興味はなかったが母を氣遣い話を振ってみたが、返ってきたのは氣のない返事だけだった。
梢は母をお風呂に入れると、ゆっくりと背中にお湯をかけた。
せっけんをとろうと手をのばすと、梢が子どものころからずっと使っていた同じメーカーの固形せっけんがそこにあった。この家はずっと変わらず同じせっけんを使っていた。
(きっと、母が見ている景色は自分とはまったく違うのだろう)
梢は、髪が薄くなった母の後ろ姿を見つめた。
(もともとうちは家庭機能不全家族なんだから、母との会話は少なかったじゃない? でも、明らかに母の言葉や表情もボヤッとして、動きも鈍くなっている……)
梢は、感じたことがない闇が重くのしかかるようで怖かった。
梢は母が寝たことを確認すると、缶ビールを開けたばこに火をつけた。
この町の夏の夜は、今でも星の瞬く音が聞こえてきそうなくらい静寂で重く蒸し暑くたれこめていた。
早朝。早起きの母に合わせて朝食の支度をするため、梢は朝五時に起きた。
外は風ひとつなく、首筋を焼かれるような日差しを予感させる晴れあがった空が広がっていた。
梢が庭で洗濯物を干していると、中学の同級生が子どもと一緒に犬の散歩をしている姿が視界に入った。
(とっくにみんな結婚して子どもがいてもおかしくない年齢だから不思議ではない。私は子どもは産まないんだろうな)
梢には、母の身の周りの世話が待っていた。
母と同じ空間にいると昔のことを思いだしてしまう。あのときの母の言葉が走馬灯のように、梢の頭を駆けめぐった。
梢が家を出て三年たったある日。母から電話があった。
開口一番、「あんた、結婚はどうなの?」と母が言った。
娘の健康を心配するような言葉、元氣にしているかという言葉はなかった。それについて傷ついているはずなのに、言葉がキツくて傷ついたとは言えず、うやむやに答えた記憶がある。いつも母は世間体や近所の目を氣にする。自分の人生に集中していない母。自分の家族を見ているようで見ていない母。昔から、この家は居心地がよくない。
梢は葛藤と寂しさを抱え、母の反応を期待して受動的になっていた。
起きてきた母に向かって、初めて思いの丈をぶちまけてみた。
「お母さん、あのときも私の体を心配する言葉はなかったよね? 娘が傷つくことを考えないよね?」
「そんなこと、そのとき言ってくれないとわからないわ。いまさら言われても記憶にないんだから知らないわよ」
無駄だった。
(たとえ母にそのときその場で言ったとしても、自分がキツい言葉を発していることは、きっと母はわからないだろう)
私のなかからさまざまな怒りが込みあげてきた。
続く……。
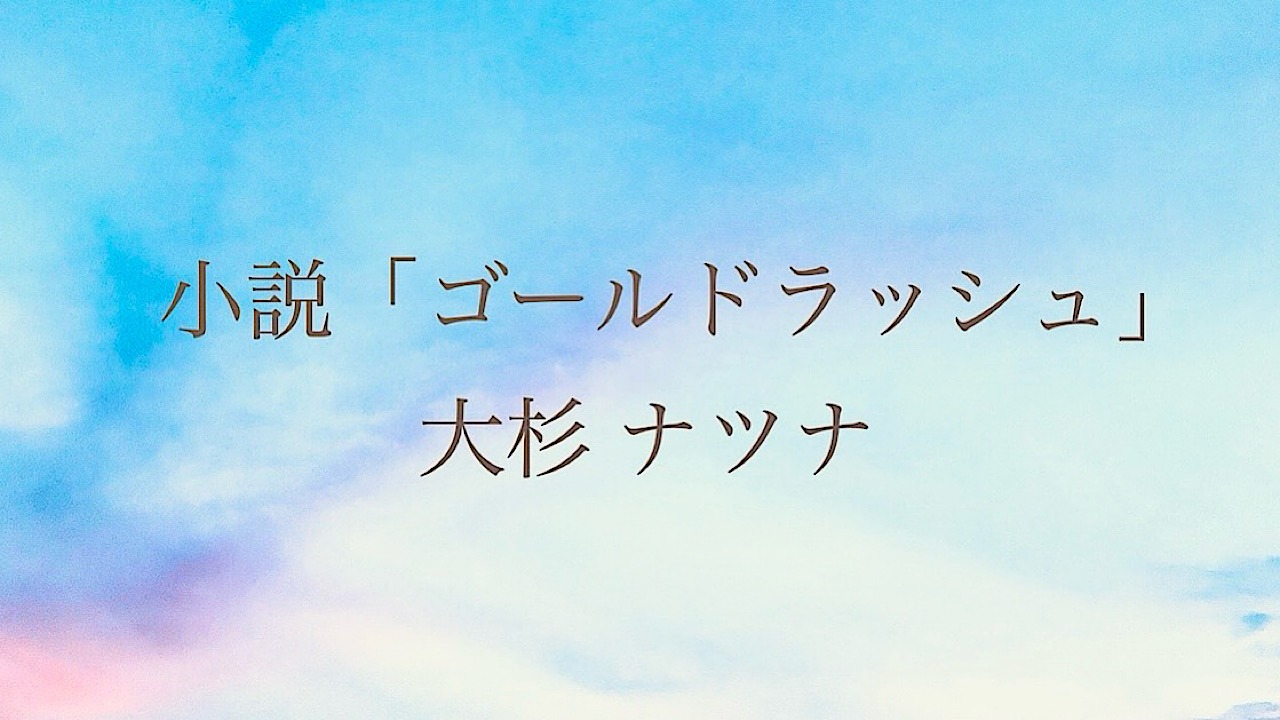
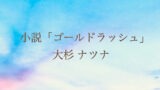
「自分を深く知る」ことをさまざまな角度から探求し、自分を癒やしていく過程で、生きづらさの原因がHSPという特性であることにたどりつきました。
このブログはHSPという特性に向き合いながら、結婚と天職を手に入れるまでの心の深海潜水夫記録です。
大人になってHSPを知り、ふに落ちた過去の思いを忘れずに書きとめておきたいと思い始めました。小説も書いています。
現在、工場で働くHSPアラフォーです。
あくまで、個人的考察です。