一カ月ほど、梢は過密スケジュールでバタバタしていた。キャンセルした分の仕事と、今の仕事を同時進行でこなさなければならなかったからだ。ようやく最近もとのペースに戻り、ひと安心していた。
ある日、梢はピアノバーにいた。
しょうすいしきった内田を励ますためだった。そして、自分も何かに寄りそってもらいたかった。
(私はピアノ演奏を聴きたくなったのかな? 本当は内田本人に会いたいんじゃない? すでに離婚していたとはいえ、別れた女房が亡くなったときにこんなこと考えるなんて……。でも、私だって希子と結婚する前から内田さんを好きだった。だけど、希子と結婚したから諦めた。でも今は……)
邪な思いが梢の頭を巡り葛藤した。
(今は内田さんを励ますことだけに集中しよう。昔、夢を諦めるなって励まされたし)
梢は、自分のなかに巡るさまざまな感情に無理矢理ふたをした。
二十九歳 八月
突如、母の調子が悪くなった。
自力で活動できる程度とは聞いたが、介護が必要になる予感がした。希子の死の悲しみに追い打ちをかけるかのように現実が梢から時間を奪っていく。
仕事に穴を開けることができず、兄が医者に付きそったが、結果は要介護ということだった。ヘルパーを頼むこともできるが、補助を受けるにも限界があった。
兄は仕事が忙しいと取りあってくれなかった。(兄の頑固な性格からして、自分の意見を変えることはないだろう)
梢は渋々母の介護をすることになった。
とはいえ、女優の仕事が忙しく、週に一、二回程度しか実家に帰ることができない梢は自腹でホームヘルパーを依頼し、なんとか生活に支障のないように計らった。
(どうして母は私の邪魔ばかりするの? せっかく女優としてこれからってときに介護だなんて……)
梢の心のなかにあった母への憤りが再び怒りとして漏れだしていた。
その反面で、介護が必要になるのは歳だから仕方がない、自分でどうこうできることでもないし、なりたくて不自由になったわけじゃないと思う梢もいた。
理性と感情の板挟みにあった梢は、来週からの介護生活を考えては頭のなかにもやがかかる不快感に苛まれた。
二十九歳 二月
冬の弱々しく柔らかい日射しが静かに降りそそぐなか、梢は撮影のため鎌倉にいた。
希子の自殺から一年半という月日に梢の悲しみは癒えてはいなかったが、梢が出演する二本目の映画の撮影がスタートしていた。
梢にとって約五年ぶりの映画作品だった。
梢は休憩時間に息抜きも兼ねて鎌倉の街を歩いていた。ホッカイロを握りながら信号待ちをしていた梢の目に、見覚えのある顔が飛びこんできた。
内田だった。
離婚する前、希子たちは鎌倉に住んでいたこともあり、梢は今も元旦那の内田が鎌倉に住んでいるのかもしれないとは思っていた。
内田も梢に氣づき、駆けよって「お茶でも飲まないか?」と誘った。
近場の年季の入った喫茶店に入り、ホットコーヒーとジャスミンの工芸茶を注文した。それらが出てくるまで、お互いに何から話せばいいのかわからず沈黙が続いた。
「鎌倉で何してるの? 仕事?」
内田が話を切りだした。
「うん。ニ本目の映画の撮影なの。元氣だった?」
「うん、まあまあかな。離婚してから、希子が自殺したことを知ってショックだったよ。俺もうつになってピアノを弾かなくなった時期もあったけど、今は息子の世話で毎日忙しいけど充実してるんだ。葬式来てくれてありがとな」
「私もショックだったよ。私は母が年とって介護が必要だから、ちょくちょく実家に帰ってるの。それ以外は、ヘルパーさんに任せてるんだ。兄は家庭環境がよっぽど嫌だったのか、今でも実家に寄りつかないしね。今どこに住んでるの?」
「鎌倉だよ。コンビニに行くために信号待ちしてたら、吉川さんがいてびっくりしたよ」
「こっちこそびっくりだよ」
「今もバーでピアノ弾いてるの?」
「もうやめたんだ。昼間の会社勤めだけさ」
「そうなんだ」
「そうそう、希子の親族のほうと連絡が取れなくて、俺が遺骨を引きとって鎌倉にお墓を建てたよ」
ホットコーヒーとジャスミンの工芸茶が運ばれてきた。ジャスミン茶の独特の風味が苦手な人もいるが、梢は緊張を和らげ集中力を高めてくれるジャスミン茶を好んでよく飲んでいた。
内田は、梢が注文したジャスミンの工芸茶に興味深く反応した。
「この茶葉をカップに入れてこうやってお湯を注ぐと、白いジャスミンの花と茶葉が開いて咲いていくのが見えるんだよ。目でも味わえるってわけ」
「へーそうなんだ」
「ほら、白い花が開いていってるでしょ?」
ふたりは、カップの中の白い花と茶葉を食いいるように見つめた。
「ほんとだ、俺こういうの初めて見たよ」
「私、こういうの好きなんだ。癒やされるんだよね」
梢は、カップを鼻に近づけ、ひと口すすった。日本のジャスミン茶より漢方に近い味がした。
「うん、かわいいね」
ふたりは不思議な世界に引きこまれるかのように、そのかわいらしい花をしばらく見つめていた。その甘ったるい雰囲氣のせいか、梢の頭のなかに、ある映像が飛びこんでは消えていった。
梢はこの光景をずっと昔から知っていたような感覚に陥った。
生まれる前のどこかの人生で自分は内田を知っていたのではないか、似たような空間で同じような会話をした氣がした。
魂の記憶がよみがえる。
何について話しているのかは思いだせなかったが、確かなことは、静かな安心感に包まれた穏やかな感情がそこにあるという、流れて消えていった断片的な過去世の記憶だけだった。
言葉にならない感覚的な何かが、梢の奥底にアクセスしたようだった。
梢は、内田に友情に近い愛情を感じていた。風間社長のときのようなドキドキとしたときめきではなく、もっと深く静かな愛おしさ、言いかえれば映画の女医役を演じたときに似た感覚だ。
「こんなときに言うのもなんだけど、結婚を前提につきあってくれないか?」
内田は梢の手を両手で握った。
内田の指先を通して真剣な氣持ちが伝わってきた。細く長い内田の指先に触れると、バーでピアノを弾いていた内田の姿がありありと頭に浮かび、しばらく沈黙が続いた。
喉に潤いを与えたくなった梢は、ジャスミン茶をひと口すすろうと口をとがらせると唇の両脇にしわができた。
「一週間待ってほしいの」
「どちらにしても直接聞きたいんだ」
「うん。来週の十二時に、またここで話しましょう」
「わかった」
梢はテーブルを挟んだ向こう側の内田に、静かなまなざしを向けた。
(私だって、胸の奥でずっと好きだった。でも、希子と結婚したから諦めたのに。そして、希子は自殺してしまった……。でも、プロポーズを受けとったら、私は人間としてどうなんだろう?)
親友を失った悲しみと、内田からのプロポーズにうれしさと背徳感が交差した。
だが、背徳感を覚えながらも梢は内田にひかれていった。
続く……。
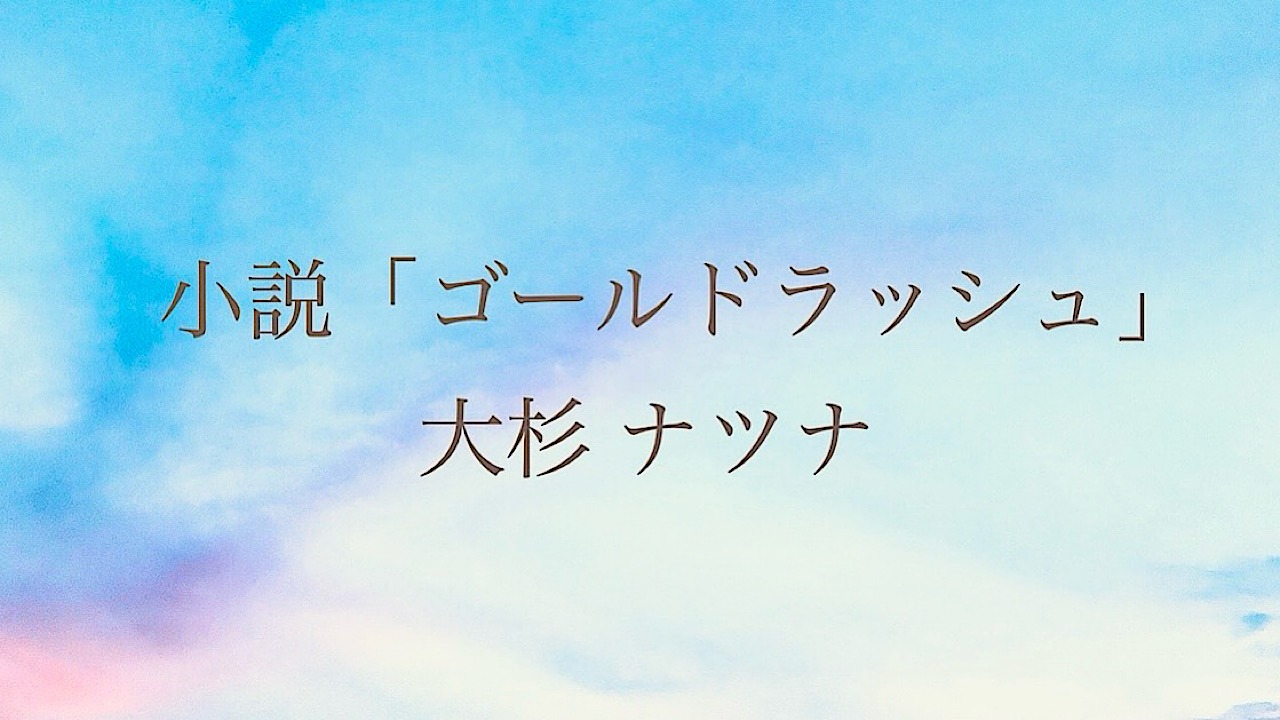
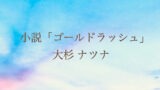
「自分を深く知る」ことをさまざまな角度から探求し、自分を癒やしていく過程で、生きづらさの原因がHSPという特性であることにたどりつきました。
このブログはHSPという特性に向き合いながら、結婚と天職を手に入れるまでの心の深海潜水夫記録です。
大人になってHSPを知り、ふに落ちた過去の思いを忘れずに書きとめておきたいと思い始めました。小説も書いています。
現在、工場で働くHSPアラフォーです。
あくまで、個人的考察です。