梢はしょうが焼きを食べおえシャワーを浴びると、ひとりでいつものピアノバーに向かった。内田のピアノ演奏が聴きたくなったのだ。
梢が店内に入ると、内田はピアノ演奏の準備をしているところだった。
(声かけてみようかな……?)
「あのーすみません、私何度かこのお店に来てて、すてきなピアノ演奏だなと思ってて……。とても心が安らぎます」
「ありがとう」
「私ホステスをやりながら女優を目指していて、演技レッスンでもうまくいかないことが多くていつも怒られるんです。でも、内田さんのピアノで励まされ、明日も頑張ろうって思うんです」
「俺の名前、なんで知ってるの?」
「ここのマスターから聞きました」
「そうなんだ。俺は子どものころからずっとピアノを習ってて、ピアノを弾くことくらいしかできないからね。君もお芝居で人に感動を与えたいっていう夢があるんでしょ? 今いくつなの?」
「二十三歳です」
「じゃあ俺と変わらないね。俺は二十五歳だよ。夢をかなえるためには、諦めず地道に努力していくしかないんだよ。今諦めたらもったいないよ」
「はい。私、絶対女優になります。ありがとうございます」
内田に励まされた梢の心は、なんだかほっこりと温かくなった。
二十三歳 六月
誕生日が近い梢は、風間社長から二回目の同伴に誘われうれしく思った。定期的にメールを送ったり、お店で話をすることはあったが、ふたりで食事するのは一年ぶりだった。いつのまにか梢の心には恋心が芽生えていた。
梢は、去年風間社長からもらった真珠のネックレスをつけていった。
「誕生日おめでとう」
「ありがとうございます」
風間社長から差しだされたプレゼントを開けてみると、Cartierの指輪が出てきた。
「僕とつきあってくれないかな?」
「えっ?」
梢も風間社長を好きなのでうれしかったが、恥ずかしさからわざと驚いて濁した。
日曜日。風間との不倫が始まった。
梢にとって、おつきあいでも不倫でも呼び方はどうでもよかった。常に戦略的な思考で頭いっぱいの脳みそを解放して、ただ目の前の喜びを素直に感じたかった。
風間の仕事が終わるとふたりは外で食事をすませて、そのままホテルに入った。
部屋に入ると風間は梢を自分の体に強く引きよせ、梢の口にザラザラした舌を差しこみ野獣のように舌を絡ませながら激しく歯茎をなめまわした。全細胞が壊れそうな情熱的なキスに力が抜けていき、梢のあそこはそれだけでぬれてしまっていた。
風間はとろけそうな梢の体を抱きあげると、そのままベッドに押したおした。
雷に打たれたような衝撃だった。頭からつま先まで強い電流が梢の肉体を駆けめぐり、全細胞がもっとほしいといっせいに喜んだ。
梢は初めて抱かれた。
風間のねっとりとした舌が唇から服を剥ぎとられた梢の胸に移動する。痛いほどもまれた梢の薄い桃色の乳首は固くなりピンと立っていた。紅くぬれた梢の本能剥きだしのあそこを、風間は指や舌で刺激した。梢のあそこはぐちゃぐちゃにぬれ、指の動きが激しくなればなるほど呼応した全身が熱くしびれ、けいれんした。
梢は腰をくねらせる。
敏感な梢の体は自然に色っぽいあえぎ声を奏でてしまう。梢は恥ずかしくなり自分の人差し指を唇に挟み声を押しころそうとした。
「お願い、電気を消して」
「このまま全部見たいんだ」
梢は、恥ずかしさと火照りで氣持ちよくなった体で葛藤した。
とうとう梢のなかに固くなったものが入ってきた。痛かった。
ピストン運動が行われるたびにパンパンと音を立てて梢の下腹部に接触する。梢は痛みと快感で必死に風間の体にしがみついた。
とても激しく動く風間の体からは、うっすらと汗がにじみでていた。
梢のなかはクチャクチャといやらしい音を立て、全身の体液や水分を搾りとられるかのようだった。シャワーも浴びずそのまま朝まで眠ってしまった。
ベッドのシーツには紅い血液がついていた。
二十三歳、梢の初体験の相手は風間だった。
二十四歳 十一月
ホステスという夜の仕事を始めて六年目になろうとしていた。
氣づけば周りは年下が多くなり、梢と同期の希子、梢より二年先にこのお店で働いている先輩の三人だけが二十代後半を迎えようとしていた。梢と年の近いホステスたちはいつのまにか辞めてしまっていた。顔を見なくなったので、解雇なのか自分から辞めていったのかはわからなかった。
十代に比べると、梢にも体力の衰えや老化が見え隠れし始めた。
ときどき視界にアメンボのような黒いものが見えるときがあり、眼科で診てもらったら飛蚊症と診断された。
眼科の医師には、加齢や目を激しくこすったりしたときなどの物理的ショックで網膜が剥がれてしまうことが原因と説明された。
「一種の老化現象ですよ」
医師は淡々と事実を突きつけた。
振りかえれば、梢はそんなことは氣にしたことがなかった。
梢は移ろう季節の変化など氣にせず、誰がいつ辞めたのか知らないまま体力の衰えはちょっと氣にして、昼ごろ起きてお客にお礼や営業のメールや電話をかけ、ときにはお手紙を書きシャワーを浴びて出勤する。そして接客しながらお酒をのみ、体型維持も肌の調子も体調管理もルーティンワークのように機械的に行っていた。何よりも自分に集中して、花のように美しくありたかった。
すべて連続ナンバーワンのプライドだった。
梢はいつのまにか細胞の隅々までホステスに染まっていた。
ある日、ミーティングでお店の料金システムを変更するという話があった。
今、ベンチャー企業や新しいビジネスなどで成功をおさめている若い社長が多く出てきているので、お店のポリシーや雰囲氣はそのまま変えず、料金設定を低めに設定し、敷居を低くして入りやすくすると説明された。ざっくり言えば世の変化や流れに乗っていこうということだった。
続く……。
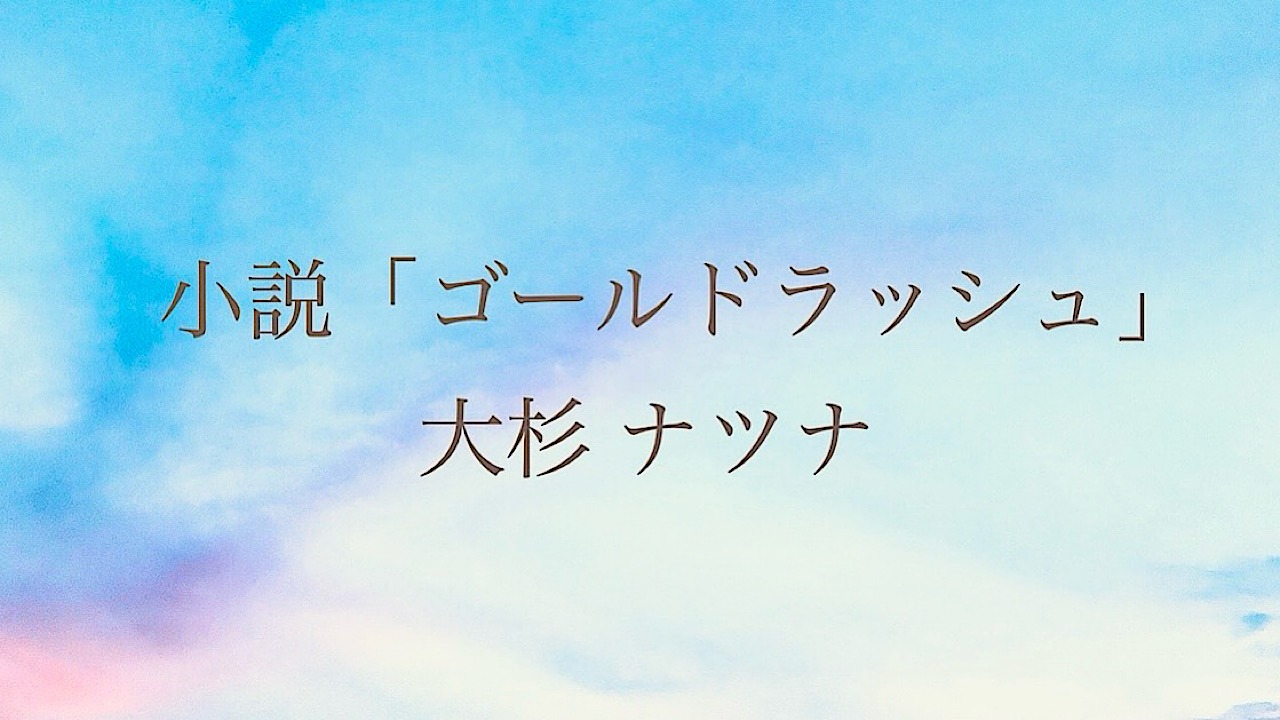
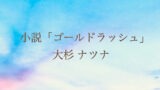
「自分を深く知る」ことをさまざまな角度から探求し、自分を癒やしていく過程で、生きづらさの原因がHSPという特性であることにたどりつきました。
このブログはHSPという特性に向き合いながら、結婚と天職を手に入れるまでの心の深海潜水夫記録です。
大人になってHSPを知り、ふに落ちた過去の思いを忘れずに書きとめておきたいと思い始めました。小説も書いています。
現在、工場で働くHSPアラフォーです。
あくまで、個人的考察です。