また、私が中学生のころ、叔母といとこがうちに遊びに来たことがあった。そのいとことはふたつ違いで、どちらかというとのんびりしている自分は活発ないとことはウマが合わなかった。
私がお風呂から上がると、いとこが泊まることになっていた。
私が髪を乾かしおわると、母が突然「隣の部屋で寝なさい」と言った。
何がしたいのか母の意図が私にはわからなかった。ふすまを少し開けられ、その日は言われるがままいつも寝ている二階の自室ではなく、ひとり隣の部屋で寝た。寝る前のぼんやりとした意識のなかで、母と叔母に囲まれ、夜中までテレビを見ながらチヤホヤされて楽しそうないとこを、ふすま越しに見ていた。
今思えばそのふすまの隙間から見える明るい雰囲気を私に見せつけたかったに違いない。
(母は、どうして私に見せつけるようなことをするのだろう? わざわざこんなことしなくていいのに。母は、それをしたら私が傷つくことを考えないのかな? やきもちを妬かせたくてやっているのなら、それはおかしい)
私は悲しかったが、どうやって自分を表現すればいいのかわからなかった。
少したってから「自分の部屋で寝なさい」と取りつくろうかのように、父が言った。氣持ちを察してくれたのか父の氣まぐれだったのかはわからないが、私は胸が張りさけそうで苦しく、また自分が情けなく悲しくなった。感情が垂れ流しの状態を早く切りぬけたい、感じたくないという一心で、完全にパニックになってしまった。
全身の力が抜けてしまった人形のようにうつむくことしかできなかった私は、階段を登る足取りがとても重かった。傷ついて寂しいのは確かなのに、染みついた我慢癖がいろいろな感情をまひさせていた。
もともと、父は物静かで人とのコミュニケーションが上手なほうではなく、母のほうが氣が強い。怒りを抑えていた部分もあるだろう。言葉でうまく表現できないところは父と似ていた。父はアルコールに依存していたから、父の人生に何か屈折したものがあったのだろうかと私は思っていた。ときどき、私は父のビールを好んで飲んでいたことがある。泡のない下の部分だけを、私がひと口ふた口と炭酸ジュースみたいに飲むことを母は嫌がっていた。
人間は何かに依存する。多少なりとも心のよりどころが必要なのかもしれない。過剰になるかならないかの差で、お酒や物欲など依存の対象は人によりまちまちだ。
「なんであのとき、“自分の部屋で寝なさい”と言ったの?」と酔っている父に聞きたかったが、ついに聞けずじまいだった。自己表現したら母に笑われるんじゃないかと怖がる弱い自分と、痛くもかゆくもありませんと母に屈しない強気な自分が心のなかで葛藤していた。
母は、私にこんな娘に育ってほしいと日常生活の態度にそれとなく入れてくる。この件に関して言えば、母はやきもちを妬く子どもらしい天真爛漫さを私に求めていたのかもしれない。しかし、私の真の部分はコントロールされない、誰にも侵すことのできない神聖な部分を私は保っていた。私は感情を表に出せない分、自己表現ができなくて周りに流されてしまう。言葉を発しようとすると、なぜか泣きそうになり、言葉が出てこなくなる。
(人は、なぜあんなに楽しそうに笑えるのか、本当に心から笑っているのだろうか?)
私には理解できなかった。母が求めている理想像も理解できなかった。
私はどこをどう組みかえるのではなく、取りかえるのでもなく、何もかも全部まとめてごっそり捨ててしまいたいくらいだった。
(おまえらに何がわかる!)
私は怒りをエネルギーに変え、表面上は何食わぬ顔をして反骨精神だけでずっと生きてきた。生まれてから今までの家庭環境のコンプレックスとか、周りと同じようにできないことや人を信じれず恋愛をしたことがないこととかが私の頭をずっと占領していた。
もううんざりだった。
かごの中の鳥が空に恋するかのように、高校二年の私は退学届けを出し未知の世界へら飛びだそうとしていた。
□■□∞∞────────────────────────────────∞∞□■□
第一幕 〜溺れた女が救助される〜
十七歳
誕生日が過ぎ、梢は十七歳になった。
午前の夏空はトルコ石のようだった。
梢は高校の夏休みや冬休みにアルバイトでためたお金と、親からのお小遣いの貯金のいくらかを手にとうとう上京を決意した。アルバイトをすることに両親は反対していたが、このときのために親に隠れてアルバイトをしていた。
どこかで住み込みのアルバイトをすればなんとか生活していける、どうにもならなかったら新聞配達所に住み込みで働けばいい。
そうして決めたのが新聞配達のアルバイトだった。芸能界で有名になったとき、新聞配達をしていたことがバレても悪いイメージはつかないし、新聞を読んだ限りでは、新聞配達以外に住み込みの職種でよいものはなかった。
新聞の募集広告を切りとると、梢は電話をかけた。
すぐに面接日が決まり、日帰りで東京に行き面接をしてもらった。
「なんで新聞配達をしようと思ったの?」
支店長は優しく聞いた。
「女優になるためにレッスンに通いながら住み込みで働けるところを探していて、新聞でこちらの募集を見ました」
「そうなんだ。うちには音楽をやっている学生が多くて、同じ境遇の人がほとんどですよ」
梢は少し安心した。
家に帰ると梢は両親には女優になりたいことはいっさい言わず、住み込みで新聞配達をするのであいさつの電話だけしといてほしいと伝えた。そこに信頼関係はなかった。
未成年の梢はパーソナルスペースを侵されたくはないのに、親の許可がなければ何もできないのが悔しかった。縁を切るつもりで、梢は自分の小さいころのアルバムやらいろいろなものを段ボールに詰めこんだ。
専売所のほうには今月末に先に自分の荷物が届くということを電話で伝え、両親が反対しても半ば強引に自分のやりたいことを押しとおそうと、まとめてあった自分の荷物を引っ越し業者に運ばせた。
さすがの両親もあきれたのか、うるさく言うこともなく静かな時間が流れた。
父と母は仲良くはない。親と娘も仲良くはない。話し合いもしない、バラバラな家庭だった。
「父親のくせに情けない、お父さんはもっとリーダーシップをとって家族をまとめていたのに」
母はいまだに自分の父親と比べては罵倒していた。
こういうときだけ、母は私のことを父のせいにする。
(こんな状態にしたのは誰だよ! おまえの言葉がキツいんだろう、傷つけてきたんだろう! バカか!)
梢は怒りと悲しみを奥底に閉じこめた。
そして、八月に上京することに決めた。
続く……。
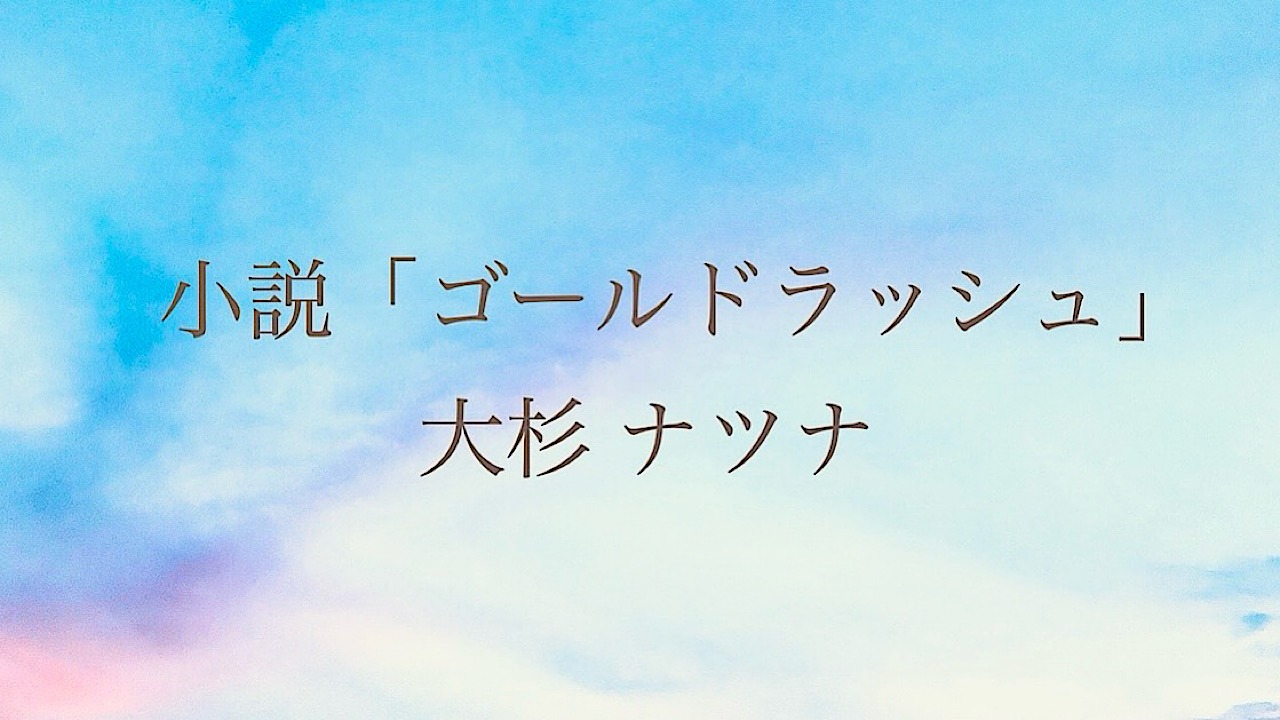
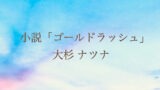
「自分を深く知る」ことをさまざまな角度から探求し、自分を癒やしていく過程で、生きづらさの原因がHSPという特性であることにたどりつきました。
このブログはHSPという特性に向き合いながら、結婚と天職を手に入れるまでの心の深海潜水夫記録です。
大人になってHSPを知り、ふに落ちた過去の思いを忘れずに書きとめておきたいと思い始めました。小説も書いています。
現在、工場で働くHSPアラフォーです。
あくまで、個人的考察です。